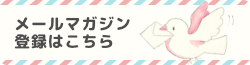発達障害を含めた多様な発達のお子さんの理解と支援をお手伝いします。
- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
お礼の手紙
2017/01/19昨年の12月、群馬県館林市の保育士さんの講演会にお招きいただきました。
館林保育研究会さんの主催でした。
70名ほどのご参加がありまして、疑似体験、演習、遊びなど盛りだくさんに
学んでいただきました。
帰りには素敵なお花もいただきまして
本当に楽しい時間を過ごせました。
今日、主催いただいた会の園長先生から
お礼の手紙をいただきました。
皆さんからの感想もいくつか記載していただきまして
「わかりやすいお話でズバリ私たち保育士が知りたいことや困っていることへのアドバイスをもらえて
有意義な時間でした」
「発達の木になる子供について、どうしたらよいのか悩んできた時に、藤原先生の講演会があり、とても勉強に
なることばかりでした。その子にあったかかわりを丁寧にゆったりとして気持ちで保育をしていこうと思いました」
「実践できる脳の働きを促したり、多動性を知る指標となるあそびを楽しむことができ、園でも実践していきます」
「気になる子のコミュニケーションにも要求や注目などそれぞれ違う意味があるということを実感できました」
「子どもたち同様に保護者の気持ちも理解し、受け止めることを忘れずに支援していきたいと思います」
最前線の現場で、真摯に子ども達に向き合い、学ぶ皆さんを尊敬し応援しています。
またお会いできる日が来ますように。
滝先生、お手紙ありがとうございました。

毎日・・・。
2017/01/18月曜日:保育園の訪問、火曜日:発達支援事業のスーパーバイズ、水曜日:保育コーディネーター研修
明日木曜日:保育士・学童クラブ指導員さんへの研修 明後日金曜日:発達支援センタースーパーバイズと
盛りだくさんの週です。





相談すること
2017/01/15今日は強い寒波がきているとのこと。
でも東京はきれいに晴れています。
我が家の長男は今日から沖縄修学旅行。
笑顔で出発しました。
さて、金曜日に、センターで実施して連続講座はご家族の支援についてお話ししました。
明日、月曜日は来年の学研「ほいくあっぷ」の取材で
ある保育園にお邪魔して、スーパーバイズしていきます。
その時の中心的テーマが、子どもへの声のかけ方・話し方について。
この連続講座も明日のスーパーバイズも
大切なのでは、相談するということです。
問題を抱えているご家族、お子さんに
どんな声をかけ、話をしながら問題を解決するのか?
つまり相談する・できるように、支援者が声掛けや話の持ち方で導くのです。
いろいろな、専門理論がありますが
「問題解決コラボレーション」というモデルが参考になります。
私も
この方法を学んで、かなり意識して子どもとの話し合いや
ご家族の面接に使っています。
3つのステップがあるのですが
最初の共感ステップがやはり何より大事です。
自分の視点と違う相手の共感するのは
やはり、トレーニングが必要だと思います。
元々の資質として、多様な人に共感しやすい方もいれば
そうでない方も。
ここも実や多様です。
また、共感の感性をあげるためには
自分の傾向をしっかり把握しておくことと
多様な発達の知識を持つことが必須です。
この内容は、来年度の連続講座
応用編夜間と、コーディネーターコースで盛り込みたいと思っています。
そのほか、今まで研修ではなかなかお話しできなかった
専門理論についても、来年度の連続講座では
盛り込んでいきたいと思います。
「問題解決コラボレーション」については、
こちらの本で学べます。

発達教育の「巻頭言」
2017/01/13
公益社団法人「発達協会」さん。
発達障害や知的障害のある子・人への医療・療育と研修・出版などをされています。
月刊誌を発行されていて、ご存知の方も多いと思います。
2月号の「巻頭言」を藤原が書かせていただくことになりました。
テーマはご家族の支援です。
ご家族を支えるためには
お子さんの困っている「その子らしさ」を通訳して
お子さんの良き理解者になっていただくこと。
支援者の役割がそこが大切ということを、書きました。
明日から、強い寒波が来るようです。
温かい家の中で読書する1日になりそうです。
事例検討:インシデントプロセス法
2017/01/11今日は、保育士さん対象の研修でした。
回を重ね8回目の研修。今まで学んできた知識を生かして
事例検討をしました。
担当のお子さんが持つ問題に対してどう支援するかを
情報を集め、分析し、支援を見出していきます。
その方法としてインシデントプロセス法という
方法を用いました。
この方法は、参加者が当事者と同じ立ち位置で
とにかく肯定的にできる支援のアイデアを出し合うというもの。
どのアイデアにも「Good!」のリアクションを返すのが約束事なのです。
ですから、安心して意見を出し合える
だって、だれも否定する人がいないから。
そのアイデアが、有効か、できるかどうかより
こうしてみたらと活発に言い合えることを大切にしている方法なのです。
最終的には出たアイデアの中から、事例提供者が使えるもの
やってみたい支援を選択すればいいのですから。
今日はこの話し合いの結果を
グループごと模造紙に記載して発表しあいました。
デスカッションしている間は、まさに白熱教室という感じ。
今日の成果の一部をを画像で載せておきますね。
楽しい研修でした。
皆様お疲れ様でした。