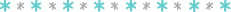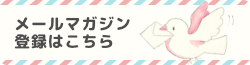- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
メールマガジン 第1号
2016/06/12メールマガジン 1号出しました。
メルマガ登録していただいた方には、、メールでお送りしました。
私も初めて書いたのですが、毎回、皆さんに役立つ情報
考えていただきたいテーマ、などあまり形を決めずに発信していきたいと思います。
初回はブログにも張り付けておきますので
QRコードから、空メールお送りくださいね。
それでけで登録完了です。

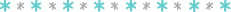
皆さん・こんにちは
梅雨なのに、真夏のような暑さですね。
体調を崩されたりしていませんか?
チャイルドフッドラボを設立してから、早くも2か月半。
皆さんに少しずつ紹介してきました。
具体的なサービスや活動は来年度からなのですが
パンフレットを、研修の機会を通じて配布しています。
その際に、お声をかけていただくこともあるのですが
ある研修後、大阪の保育園の園長先生から、Skypeを使った相談を保護者の方と一緒にお願いしたいといっていただきました。
その地域では、相談したくても、半年待ちなのだそうです。
Skypeなら、遠くても相談できると期待されていました。
そうした困っている方のお手伝いができることに、このラボの意義があります。
その先生はさらにおっしゃいました。「保護者の方と一緒に相談することで、お互いの理解が共有できる、連携もとりやすくなる」
その通りですね。園からの相談を中心に考えていた私ですが、園と保護者の方の協働に、ラボが関われるのですから、サポートの幅も広がります。
このように、ラボのサービスをこんな風に使いたいとご提案いただければと思います。
それぞれの現場の、それぞれの方々のニーズに合わせて、できるだけサービスを作っていきたいと考えています。
来年度からの研修プログラムも、現在アイデアを出して、作っています。
毎月行う連続講座、土曜日の午後と平日の夜間に実施予定です。
この講座はそれぞれ12回程度行う予定ですが
その中で7回講座を受けていただけると、発達サポーターをという資格を取得できるように準備中です。
また、Skypeのグループ通話機能を使って、子どもの発達特性について学ぶ
夜間の講座も行います。
1回1000円で参加でき、夜9時〜 10時〜の時間帯で実施予定なので
お仕事をしていても、お子さんがいても
自宅で参加できるます。学びやすいスタイルが提供できると思います。
るとさらに、ラボカフェという「お茶とスイーツを楽しみながらのケーススタディー」
を考えています。どうですか、なんだか気軽に参加できると思いませんか?
まだまだ、皆さんに学びたい、参加したい、と思っていただける研修を作っていきますね。
皆さんからもぜひ、こんなことしてほしいとお伝えください。お待ちしています。
さて、今回のメールのテーマは「多様性への寛容さ」です。
子どもの発達を支援していくためには「多様性への寛容さ」が知識や技術を持つ以前に
必要だと私は考えています。
しかし、現代社会は「不寛容社会」であるといわれいます。
たとえば、子どもの学習ノート・・虫の表紙で有名ですが
虫の嫌いな人からの意見で、虫の写真が採用されなくなった・・というのを皆さんは知っていましたか?
これが、多様性への不寛容さを象徴しているとおもいます。
虫の好きな子もいれば、嫌いな子もいる
そんな簡単なことが、まかり通らない社会はとても怖いと思います。
たぶんすべての人がそうではないと思うのですが、一部の不寛容な人の発言に
大きく反応してしまうということなのでしょう。
また、失敗についても不寛容であることが気になります。
あるタレントさんの失敗に関して過剰に攻撃してしまう。
それは、恐ろしいほどの誹謗中傷に膨らむこともあります。
この不寛容さは、大人も子供も、自尊心が保たれにくい環境に関連していると思います。
自尊心が保たれない社会で育つから不寛容なのか、不寛容だから自尊心が育たないのか
これも、鶏と卵の関係に似ているのではないでしょうか?
以前、実践障害児教育で連載していた「発達障害のある子の心を育てる」
の原稿の一部をお届けしましょう。
○「あの子だけずるい」と言わない子ども
ある保育園での昼食前、お当番が給食を配膳している、その配膳をテーブルで待っている子・・このまっている子が多数派なのだが、3名の少数派の子は、遊びのコーナーでまだ遊んでいた。「本のコーナー」「ブロックのコーナー」に分かれて一人ずつ。部屋の片隅のリソーススペースでごろごろしている子もいる。私がその子たちに近づいて、「お給食はたべないの?」と聞くと、「食べるよ、自分の時間になったら片づけるよ」と当たり前のように答える。自分の時間というのはいつなのか?様子を見ていると、配膳が終わり「いただきます」が始まるころに片付けて自分の席に着いたのである。文章で書くとなんということはない場面に思えるかもしれないが、普通ならみんなが同じように座って配膳を待つ光景が当たり前で、お当番が始まっても遊んでいる子は「あのこだけずるい」と言われるのではないだろうか?しかし、私は様々な現場でこの待ち時間にいろいろな困った行動を示す子ども達を数多く見てきた。なぜならそれぞれの待てる時間は、発達の在り方により違うからだ。その待ち時間の違いをごく自然に、環境を設定し、行っているのである。これはわかっていてもなかなかできない。そして、そのことをごく当たり前の日常にしているので、子どものたちも「あの子だけずるい」と言わないのである。こうした保育の中、自然に待つことにも多様性があり、その子にあった待つ方法を取っていると学んでいるのだといえる。
○例外もある、特別もある・・それこそが平等
この様に保育士や教師が特別支援の必要な子どもに、真摯に向き合い、温かく根気よく支援をする・・子ども達はその姿を必ず見てそこから「その子には、この場面では支援が必要なのだ」、「ぼくたちとは違う保育、教育が必要なのだ」と認識する。この特別なのだと認めることこそ、多様性への寛容さの第1歩だと思う。すると、先生がその子と向き合う時間が自分たちより長くても、ほめる機会が多くても「あの子だけずるい」といわなくなる。それは、その子の多様性を認めているからである。こうした子どもの変化に、言葉はいらないと常々感じる。様々な現場で、こうした多様性に寛容な先生たちと子ども達の生活に出会うと実感する。それこそ、日ごろの保育、教育が雄弁に子ども達に「多様性」を伝えているのだろう。
こうした保育、教育の中では、子どもは特別支援には理由があり必要なことだと感じ、時に先生と同様の支援をナチュラルにするようになる。またそうしたクラス経営をしている先生は、いずれの子も大切にしている。こうした現象が「すべての子どもの心を育てる」ということなのだろう。
○クラス全体の社会性を向上させる
ある保育園の年長組では、相手が傷つくような言葉「ちくちく言葉」が飛び交っていた。そこで、ちくちく言葉とふわふわ言葉(相手の気持ちが温かくなるような言葉)を伝え、ふわふわ言葉を使うクラスになろうと先生が提案した。その上で、きれいな透明な瓶と、ビー玉をたくさん用意し「ふわふわ言葉をいったら、言った子にはこのビー玉をあげます。ビー玉をもらった子はきれいな瓶にビー玉をためてね。良い行動の貯金だよ。全部たまったら、園長先生にお給食を一緒に食べてもらおう、ほめてもらおう」と伝えた。すると、すぐに子どもたちがふわふわ言葉を使い始め、そのたびにビー玉を嬉しそうに瓶にいれるようになった。瓶はあっという間にビー玉で一杯になり、園長先生からたくさんほめてもらい、楽しくお給食を一緒に食べた。ちくちく言葉はすっかり消えてクラスが温かい雰囲気に包まれるようになった。キラキラ光るビー玉のなんときれいなこと、子どもの心を写しているようであった。
違いを認め合うことと、クラス全体に温かい雰囲気を作ること、全ての子どもの心を育むこと、こうした試みが様々な現場でされている、しかし、何より大切なのは、その試みをする大人が違いを認め、「みんなちがってみんないい」を体現することなのだと思う。
多様性への寛容さも脳の資質と関連しているのです。知っていましたか?
でも、脳は発達するわけですから、寛容さに向けて脳の成熟度を増していきたいものです。
チャイルドフッド・ラボ
所長 藤原里美