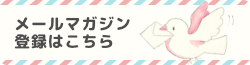発達障害を含めた多様な発達のお子さんの理解と支援をお手伝いします。
- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
保育コーディネーター研修 初回でした
2016/05/11今年度は5市の行政サイドのご協力をいただき
保育園に特別支援コーディネーターの役割を果たせる
保育コーディネーターさんを誕生させようと
9回の系統だった研修を実施することとなりました。
今日はその第1回。
2市から60名弱の保育士さんが参加されました。
蒸し暑い午後にも関わらず
皆さん熱心に聴講いただき、たくさんのメモをとられていました。
演習やグループワークも盛り込みながら
楽しく学をモットーにあと8回がんばります。
ご準備いただいたスタッフの皆さま
気持ちよく研修ができたのは皆さんの力が大きかった。
ありがとうございました、そして次回もよろしくお願いいたします。

研修15分前
開始までには満席になりました。
日本保育学会 第69回大会
2016/05/07今日も快晴。
今日、明日と東京学芸大学で、日本保育学会があります。
今日の午後、口頭発表と、座長をつとめてきます。
保育士さんの特別支援コーディネーターを育成する研修
「保育コーディネーター研修」と私は名付けていますが
その実践と効果について報告してきます。
多様な発達を子どもたち、を含めた保育には
専門的な知識と技術を持った保育士さんが現場に必要なのです。
専門家のスーパーバイズの回数はあまりにも少ない現状。
それぞれの園にこうした核になる人材が求められます。
この研修については、今年度も9回の実践的かつ系統的な研修を
5市で実施予定です。
それぞれの現場で活躍できる「保育コーディネーター」さんを
育成したいと思います。
これらの活動や研修についても随時ご報告していきます。


研修のご案内
2016/05/02研修のご報告とご案内です。
4月30日は、宮崎でこども家族早期発達支援学会の研修がありました。「発達を支援するということ」「環境の支援・行動の支援」
2つの講座を担当しました。
鹿児島、福岡、大分からもご参加いただき、ありがとうございました。
「早期発達支援士」資格取得を目標に、熱心に受講されていて、私も話に熱が入りました。
今月からは、都立小児総合医療センターで様々な研修が始まります。
東京都子どもの心拠点病院事業の研修なので、無料で受講できます。
https://kodomo-no-kokoro.jp/
のHPより、案内申し込みなどができますので
ぜひ参考にされてください。
ただし、どの研修も支援者対象のものとなります。
5月13日金曜日午後は「アセスメント」の研修。
発達検査や知能検査などフォーマルなアセスメントと
観察を中心としてインフォーマルなアセスメントを
両方学べます。
E-leaning
2016/04/29昨年度から、教員免許状更新講習の講師を引き受けています。
今年度は、その講習をネット上で行うE-leaningにするということになりました。
より多くの方に、講習を受けやすい方法で受講いただくということが目的の一つです。
でも、私の講習は双方向であり、多くの演習を入れるのが特色なので
それが一方通行になりがちなE-leaningでできるのか?というのが課題でした。
お引き受けするかすこし、悩みましたが、ある意味チャレンジして、双方向のE-leaning
を試みようと思いました。
また、演習もいくつか入れながら、足りない部分はこちらで演習をしている状況を
動画で流して参加している感覚を持ってもらいながら、学びをすすめていただけるようにと
構成を考えました。というか、このブログを書いている今まさに、その構成にとりくんでいるのです。
75分4ユニットの構成です。
一度作ったパワポのスライドを、書き換え書き換えしています。
スライドの編集をしていただいている、プロの方には、何度もスライドの修正が入り
本当に大変な思いをさせていると思うのですが。
E-leaningはある意味エンターテイメントだと思います。
学びは楽しくないといけません。楽しい面白いと思いながらみていたら
あっというまに75分経っていた。そんな、内容になればと長いつつ。
撮影は5月中旬、ぎりぎりまで、この作業が続きそうです(笑)
明日、厳密にいうと今日ですが
宮崎で学会主催の研修があります。
私は30日に2コマ担当します。
宮崎の皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。
藤原でした。
安心して話せる大人
2016/04/26こどもは感性が豊かです。
発達障害のある子どもたちは、自分が生き抜くために
とても鋭い感性をもっているなあと
感じることがあります。
サバイバルスキルとでもいうのでしょうか、この人は信頼できる
信頼できないという感覚を、的確に判断しているという感じです。
こどもに安心感を与えられる人になりたいと
常に考えている私です。
どうしてかというと、その人に安心感を感じられないとこどもは自分の感じ方を
素直に表現してくれないからです。
私たちと違うものさし・・独自のものさしをもっている場合
そのものさしを、率直に教えてもらえないと適切な支援につながらないのです。
もちろん、日頃は大人が多分こうだろうと仮説を立てて、支援していくのですが
本人から教えてもらえたら、これほど楽で、正確な情報はありません。
ここで大切なのは、支援者が「多様性への寛容さ」、「柔軟なハート」をもつことなのです。
それを、自分の胆(きも)として据えているかどうかです。
ここを子どもたちは見抜くのだと思うのです。
この胆の据わった人になれれば、子どもは安心して、素直に話してくれると
私は信じています。
自分のものさしを横に置いて、子どものものさしを大切に大切に扱うことです。
そして、子どものものさしを尊重する感性を磨くことです。
<大切なあなたへのメッセージ>
私を信じて、自分のものさしについて話してくれた君。
私はあなたの力になりたいと思っています。
これからも、必要な時はどうぞ話に来て下さい。
いつでも待っています。
あなたの身近なサポーターより